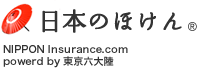ペット保険比較トップ > ペットと保険のコラム > 必ず知っておいて欲しい。犬の老いや終末医療について

愛犬との生活を悔いなく最良のモノにするために
必ず知っておいて欲しい
犬の老いと週末医療について
毎日愛らしい表情や仕草を見せてくれる愛犬も年を重ね、いつかは、虹の橋を渡ります。
ただ、すべての犬が老衰で眠るように亡くなるというわけではなく、人間と同じように、病気の治療や介護などで家族が大きな負担を強いられることもあり得ます。そのため、こうした老犬を保健所に持ち込むような心無い飼い主もいます。おそらく、無知から何の備えもしなかったり、安易に飼育を始めたことが原因といえるでしょう。
今回は、飼い主なら知っておきたい犬の老いと高齢犬の終末医療についてまとめてみました。
1. 犬の平均寿命と老いのスピード
犬は大まかに小型犬、中型犬、大型犬に分けられそれぞれのグループで平均寿命が異なります。ここに超小型犬・超大型犬を加えた平均寿命を以下よりご確認ください。
— 犬の身体サイズごとの平均寿命 —
■超小型犬(体重5㎏未満):13.8歳
■小型犬(体重5㎏以上10㎏未満):14.2歳
■中型犬(体重10㎏以上20㎏未満):13.6歳
■大型犬(体重20㎏以上40㎏未満):12.5歳
■超大型犬(体重40㎏以上):10.6歳
参照:アニコム損保 動物白書2016犬の身体サイズごとの平均寿命
(https://www.anicom-page.com/hakusho/book/pdf/book_201612.pdf)
体重が小さいと寿命が長く、超小型犬を除けば体のサイズと犬の平均寿命は相関性があることが読み取れます。平均寿命が最長の小型犬で14.2歳、最短の超大型犬が10.6歳なので、ヒトの寿命を80年程度とした場合、犬の老いの速さは、ヒトの6~8倍となります。
小型犬は見た目も愛らしくポメラニアンやトイプードルなどは、とても高齢犬に見えないことがあり、年齢を聞いてびっくりするケースも多々あります。
サイズが大きくても長寿のケースもありますが、一つの指標として上記の表を参考にすることができます。20歳を超えるような長寿犬もいますが、それでも犬の平均寿命は、人間の平均寿命の1/4程度なのです。
2. 犬の老年期(シニア)はいつから?
犬の老年期(シニア)は、小型・超小型・中型で8歳くらい、大型犬、超大型犬で5~6歳といわれています。健康な犬の場合、外見上とても若々しく、シニアなのかわからないケースもありますが、犬が老いてきたかの確認にはいくつかのポイント(老化のサイン)があります。
1. 散歩にあまり積極的になくなった
運動に対して積極的でなくなり、散歩に出てもゆっくり歩くようになったり、ドッグランでもあまり走らなくなります
2. 食事の量が減った
間食を求めたりすることや、食事を残すことが増えます
3. 飼い主の声に反応が遅くなった
老齢から耳がとおくなり、飼い主の声に対しての反応が遅くなります
4. 被毛に白髪が増えた。
加齢とともに白髪が増えます白毛の犬では分かり難いのですが、黒色の犬だと顔の毛に白髪があることに気が付くことがあります
5. 寝ていることが多くなる
若い頃はせわしなく動いていますが、老齢になると昼寝の時間が長くなったり、声をかけても起きないことがあります
6. 目が白濁してくる
核硬化症と呼ばれる、老化現象です。目の色が変わってくるケースがあります
7. 歯が抜ける、歯茎が細くなる
歯の異常は気が付きにくいもの。歯のケアを頻繁に行っている飼い主の方は気が付くことがあります。加齢とともに口腔内に異常が出始め、口臭が気になってきたら何か異常がある可能性があります。高齢になると虫歯や歯肉炎などにより、歯が抜ける、歯茎が細くなるなどの症状が出やすくなります。
以上の7つ以外にも老齢のサインはありますが、同時に病気や体調不良のサインである可能性もあります。シニア期に差しかかりいつもと違うと感じたら、動物病院で健康診断を受けることを考えましょう。
3. 老犬の終末期と終末医療について
人間と同じように犬も大きな病気などにより長期間の治療や介護が必要となるケースがあります。飼い主は、愛犬の終末期と向き合う形になります。
以下では終末期に起こり得ることと終末医療についてまとめてました。
4. 終末期に起こること
終末期になると、「持病の継続的な治療」や「日常生活に対して介護」が必要となります。特に持病に関しては、完治の見込みが薄いケースもあり、金銭的にも飼い主には負担になります。
高齢犬のかかりやすい病気と終末医療
高齢になるとかかりやすい病気・ケガは、「心疾患」「肝疾患」「腎疾患」などです。また、「糖尿病」や「クッシング症候群(副腎皮質機能亢進症)」「甲状腺機能低下症」などの内分泌疾患や各部位の「悪性腫瘍(ガン)」も注意が必要で、避妊・去勢を行っていない場合、「前立腺肥大」や「子宮筋腫」を罹患することがあります。こうした病気の症状がなく健康な犬でも、歳を重ねたことで関節に痛みがでてくることもあります。
また口腔内の異常も高齢になると要注意です。「歯周病」などを患っていると歯がグラグラしてきて、歯が抜けてしまいます。この繰り返しで最後はほとんど歯が残らないこともあります。歯周病については心臓疾患との関連性もあり得るため(歯磨きが苦手な飼い主の方は多いですが)、口腔内ケアは重要です。
その他に注意したいものには、「認知症」があります。人間の認知症と同じように現在の医療で、完治は望めません。
高齢になるとかかりやすいこれらの病気・ケガはどれも完治や根治は難しく、再発なども含め長期治療や病院への入院や最悪「安楽死」をさせるといったことを覚悟する必要があります。
安楽死について
安楽死については、一般的ではありませんが、治る見込みもなく毎日愛犬が苦しむ姿を見ているのは、辛いものです。獣医師との間で以下のような認識、同意があれば安楽死の手続きが行われます。
1. 愛犬が生きることに苦しみや激しい痛みを感じており、それを回避する方法、治療方法が無いこと
2. 安楽死に対して、飼い主である家族全員の同意が得られていること
安楽死については賛否あります。非常に難しい問題のため、当サイトでは否定も肯定もできませんが、実際に愛犬が苦しんでいる辛い状況に置かれたらと考えると、一概に責めることは出来ないのではないでしょうか。
犬の終末期の医療についてはこうした辛い選択をしなくてはいけないこともあると認識することが大切です。(同列に語るべきことではありませんが、2019年10月22日、ベルギーのパラリンピック選手が40歳で安楽死によって死去されました。ベルギーでは人間の安楽死が法律によって認められています。)
犬の介護について
老齢とともに日常生活に関しての介護が必要になることがあります。以下が一般的な介護の例です。
1. 歩行について
歩くことが難しくなり、カートでの散歩となることもあります。室内では足元がおぼつかなくなることもあるので、転倒防止のため滑りにくい床やじゅうたんに変えることが必要になります。
2. 排泄について
排泄のタイミングが間に合わず、お漏らしをしてしまうこともあり、おむつの着用や排せつの介助が必要になることもあります。
3. 食事について
噛む力が衰えるため、できる限り小さい粒のものやお気に入りのフードを砕いて食べやくする必要があります。また、自力での食事が難しく流動食の場合は、シリンジ(針のない注射器)を使うと上手に食べさせられます。
4. 床ずれの介助
足腰が悪くなったりすることで寝る時間が増えたり、犬が寝たきりになると長時間同じ姿勢になるため、腰や肩、足の関節など、体重のかかる部分の血流が悪くなり、床ずれができやすくなります。 飼い主が一定の時間を見てケアすることも重要ですが、一カ所に体重が集中しないように、床ずれを予防するためには、ベッドを柔らかいものに変えたり、床ずれ防止のマットやクッションなどを活用しましょう。
5. 介護に関する飼い主の負担
高齢から終末期に介護が必要になったケースでは、飼い主にも様々な負担が発生します。
肉体的・時間的負担
介護に関わることになると、肉体的負担がかかります。犬だからと安易に考えているようであれば、考えを改めるべきです。
小型犬であれば体重が軽いため、抱き上げたり、行動を静止するなどにさほど肉体的負担は発生しませんが、中型犬以上になると10kgを超え、抱き上げたり、痴ほう症などで暴れるなどがあった場合相当な負担がかかります。
また、救急で病院に行くことや、床ずれのケアのため定期的に時間を割く、痴ほう気味の場合は夜泣きに起きてなだめたりすることもあるため、睡眠時間が削られ、体力的にも、時間的にも負担が大きくなります。
飼い主の年齢も犬とともに上がるため、こうした介護は、中高齢の飼い主にはかなりの負担になると考えられます。
金銭的負担。
薬代を含めた治療費やカートなどの介護用品、室内の改修など、それ相応の出費がかかります。がん治療や心臓疾患の治療だと、長期間に渡っての治療は相当な費用がかかります。
こうした医療費については、ペット保険という手段もありますが、病気がある状態や高齢になってからでは加入ができません(ペット保険会社によります。細かい規定は各ペット保険会社へご確認ください)ので、注意が必要です。
心理的負担
愛犬が変わっていく様子や苦しむ様子を毎日見ていると、看護する側の心理的負担も大きなものになります。また、愛犬が虹の橋を渡ったあとは、ペットロスになる方もいらっしゃいます。できる限り複数人で介護にあたることや、獣医師も含め相談相手をもつことが重要です。
過ごした時間が長ければ長いほど、愛情が深ければ深いほど、飼い主の負担はとても大きいものになります。できる限り一人で抱えこまずに、複数人で介護に臨むことが重要です。
また、ペットと飼い主の老々介護になってしまうようであれば、現在は、老犬ホームやホスピスなどもありますので、選択しとして検討するのも大切です。
6. まとめ
犬の老化のスピードや高齢期や終末期にどのようなことが起きて、どのような負担が発生するのかを知っておくことで、愛犬が若い段階から様々な備えができます。
事前に介護に臨める体制を考えておくことや、ペット保険や貯金などの備えをしておくことで、飼い主も愛犬も充実した高齢期・終末期を迎えられます。
また、終末医療については、最善の選択ができるのは、愛犬と長く過ごした飼い主だけです。どこまで治療するのか、苦しませないためにはどうすればいいのか、悩んだ末にどんな選択をしたとしても、間違いではないでしょう。
最後の一瞬まで、愛犬とともに悔いなく過ごせるように、できるだけのことを行い、見守ってあげましょう。。
高齢犬でも入れるペット保険比較
前述したように、品種ごとの寿命に大差がない猫とは異なり、犬の場合は品種ごとに平均寿命が異なり(体重と寿命に相関関係が見られ)ます。小型犬は長生きの傾向があり、大型犬はそれに比べると寿命は短めです。
シニア、高齢犬と呼ばれるのは小型犬で概ね8歳頃、大型犬で5、6歳頃です。
当サイトの「ペット保険比較・プロ版」で確認すると、新規申込みができなくなる制限が概ね8歳から始まりはじめます。(新規加入の際は健康に関する告知事項があり、持病があったり、ケガや病気をして間もない場合、また過去に特定の病気に罹っていた場合などでは契約に差し支えがある場合があるので注意が必要です。)

ペット保険比較ページ
【ペット保険募集代理店】
合同会社東京六大陸
神奈川県鎌倉市長谷2-1-7 サテライトユイガハマ R2
【代理店の立場】
当社は保険会社の代理店であり当サイト上で保険契約の締結の媒介を行うものです。保険契約締結の代理権および告知受領権は有しておりません。
保険契約は、お客さまの保険契約のお申込みに対して保険会社が引受けの承諾を行った場合に限り成立します。